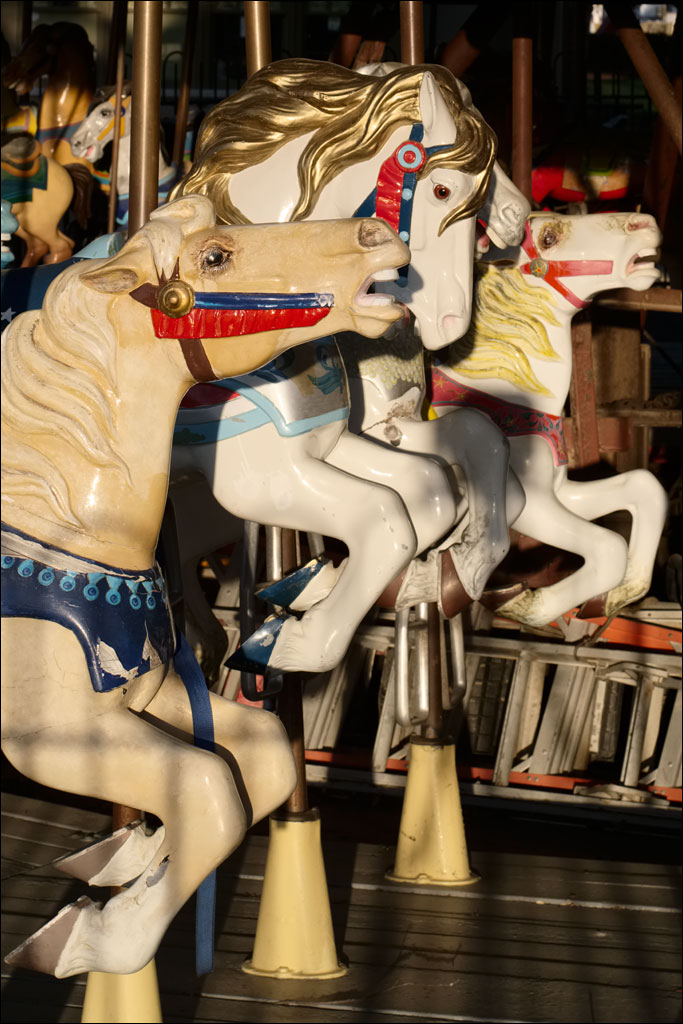ギアトーク 1~ 9 では、
使ってきたカメラやフォトテクニックなどを紹介しています。
(メインメニューの「Resources」の「ギアトーク」で、掲載後は、いつでもご覧になることができます。)
Wista 45VX(ビスタ45VX) テクニカルカメラは、金属製平底式カメラです。前部スタンダード(レンズボード保持枠)を使って、ライズ、シフト、スイング、ティルトのあおり、後部スタンダード(ボディ本体)を動かすことで、スウィング、ティルトのあおりが可能です。長尺レールもあり、頂点距離が最も長いものから短いものまで、幅広く使えます。蛇腹をたためば、とても頑丈でコンパクに変身します。
Wista 45VX で撮影した画像はこちらです。
このカメラのすばらしさは、画像の質のよさだけではありません。パースペクティブとフォーカスプレーン(ピントを合わせる範囲)を、かなり自由に決めることができます。
フイルム面(後部スタンダード)で、パースペクティブ、またはフイルム面とレンズ面、物面の線がどのように一点に収束するかを決めますが、もっとも基本的なのは、ビルの線を平行にすることです(下の画像を見てください)。フイルム面は、ファーカスプレーンもコントロールしてます。レンズ面(または前部スタンダード)は、どのようにフォーカスプレーンが被写体と交わるかを決めます。
物面の画像をシャープにするためには、二つの基準があります。レンズ面、フイルム面、物面が平行な場合(A)と、 1点に集まる場合(B)です。(B)はシャインプルーフの原理( Scheimpflug Rule)と呼ばれていて、主に、パースペクティブと焦点のゆがみを利用して、クリエィティブな画像をつくるために使われます。
フィルムの魅惑
4×5 のフイルムは、一度使いだすととりこになってしまいます。ライトボックス上のポジとネガの質の良さといったら、特に小さなフォーマットのものに比べると、官能的といっていいぐらいです。
ただ、大判のフイルムを使うと、カメラやレンズだけでなく、その他の必需品(シートフィルムホルダー、かぶり布、三脚、アームカバー、ルーペなど)も、大きくなってきます。
フィルム取り扱い上の問題
フイルムの取り扱いは、ちょっと面倒です。フォルダーには、たった2枚のフイルムしか入れることができません。それで、複数のフォルダーをいっしょに運ぼうとすると、重くなりかさ張ってしまいます。野外での撮影には向いていません。加えて、アームカバーをつけて、フイルム交換をするのに適した場所を見つけることも必要となってきます。
僕は、 6×6 と 6×12 のフイルムバックを装着して使うことで、この問題を少しですが、クリアしました。フイルムタイプが何であろうと、大判カメラはシステムサイズも大きいです。でも、ゆっくりとした撮影ペース、そして画像のコントロースが効くという点で、とても魅力的です。