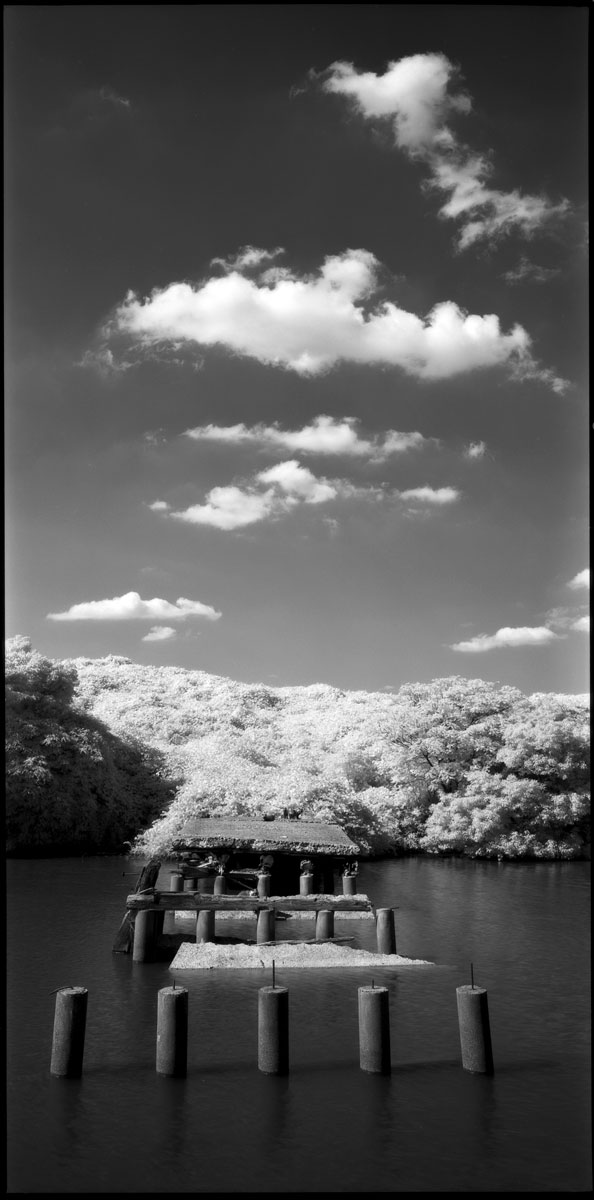イワミツバ、野生のレタスに続いて、食べられる雑草&野草シリーズ。
今回は、「野生のすみれ」。花だけでなく、葉も食べられるものがある!
うちの庭に生えているのは、北米でもっともよく見られる、和名はビオラ・ソロリア ‘パピリオナケア’(アメリカスミレサイシン)というすみれで、英名は、Common Blue Violet、学名はViola sororia。青紫だったり、白っぽい花が咲く。もちろんこのかわいい植物も、繁殖力が強いので、芝生が命の社会では雑草とされている。日本でも見られるし、園芸店でも売られている。
このスミレの「花と若葉」は食べられる。このあくの強そうな葉も食べられるとは‥‥。
日本でも、花は食用とされているが、葉が食べられると書いてあるサイトは稀のような。アメリカのこの手のサイトでは、あたりまえのように野生のすみれの葉が食用として紹介されている。ほとんどの「野生のすみれ」の葉と花は、食べられるらしいが、食べられないものもある。たとえば、黄色の花をもつ種類の中には、吐き気や下痢を起こすものもあるので、食べない方がいい。すみれは種類もたくさんあるので、識別には、専門家に相談しよう。
さて、数ヶ月、迷いに迷って、ついに庭のビオラ・ソロリア ‘パピリオナケア’を食べてみた感想はというと‥
葉は、
春の初旬から中旬の「若葉」、または秋の「若葉」のみが、おいしい。生の若葉は、あっさりとしたマイルドな味なので、食べてみると驚くかもしれない。生のまま、サラダやスムージー、サンドイッチに混ぜて使っている。軽く炒めたり、ゆがいて、パスタやオムレツなどに入れることもある。葉には、ビタミンアAとCが豊富らしい。他の葉っぱ類といっしょに食べたほうが、食べやすい。夏に向けて成長しはじめると、苦くて固くなり、まずい。カタツムリにゆずってあげよう。
花は、
砂糖漬けだけでなく、たくさんとってジャムにしたり、ハーブのように酢につけたりする人もいるが、面倒なので、自分ではしたことがない。もちろん、生の花をサラダにも入れられる。花には、ビタミンCがあるらしい。
花も葉も、
乾燥させてお茶として飲めるらしいが、これはやったことがない。今年こそはやろうと思っている。花の色がでるお茶が楽しみだ。
薬草としても、チェロキー族に使用されていたとする英文サイト等があるが、自分は薬用としては使っていない。使用して効果があったら、載せようと思う。
花を見ているだけでも、かわいくて、幸せな気分にしてくれるビオラ・ソロリア ‘パピリオナケア’(アメリカスミレサイシン)。花と葉もいただけて、多年草だなんて、すばらしい! 我が家では、もうべビーリーフ待遇を受けている。
注意:葉と花以外は、食べてはいけない。